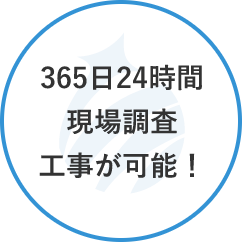大阪のマンション・大規模修繕・ベランダ防水工事

Column
Column
お役立ちコラム
-
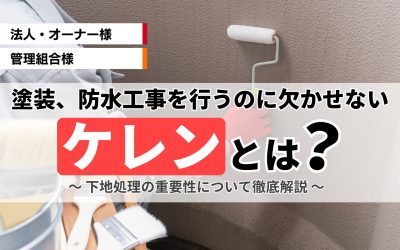 お役立ちコラムもっと見る
お役立ちコラムもっと見るケレンとは?下地処理の重要性を知り、耐久性と美観を守るための徹底ガイド
更新日:2025.06.18
-
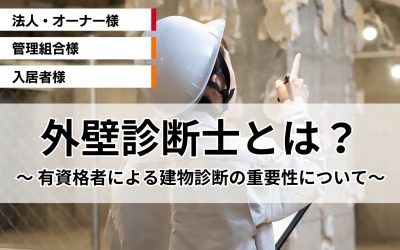 お役立ちコラムもっと見る
お役立ちコラムもっと見る外壁診断士とは?有資格者による適切な建物診断の重要性と意外なメリット
更新日:2025.06.18
-
 お役立ちコラムもっと見る
お役立ちコラムもっと見る外壁材の種類と選び方:メリット・デメリットを比較して最適なものを探そう!
更新日:2025.06.18
-
 お役立ちコラムもっと見る
お役立ちコラムもっと見る雨漏り診断士とは?有資格者による適切な建物診断の重要性と意外なメリット
更新日:2025.06.18
-
 用語説明もっと見る
用語説明もっと見る感謝の会2023が開催されました!
更新日:2025.06.09
-
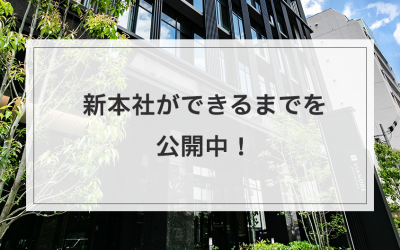 用語説明もっと見る
用語説明もっと見る新本社ができるまでを公開中!
更新日:2025.06.09
-
 用語説明もっと見る
用語説明もっと見る大規模修繕の責任施工方式って?メリット・デメリットまで徹底解説!
更新日:2025.06.18
-
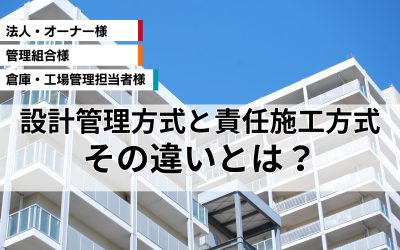 用語説明もっと見る
用語説明もっと見る設計監理方式と責任施工方式の違いとは?
更新日:2025.06.18
-
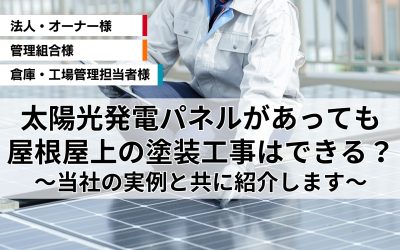 用語説明もっと見る
用語説明もっと見る太陽光発電と屋根塗装
更新日:2025.06.18
-
 用語説明もっと見る
用語説明もっと見る修繕と改修の違い
更新日:2025.06.18